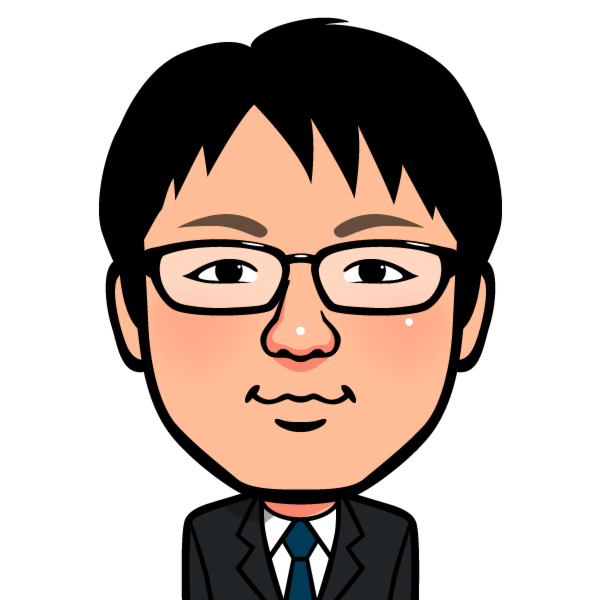日曜ブログの134回目
先日、会社の忘年会を行いました。
毎年だいたい盛り上がってしまうので、
周囲にご迷惑をかけないよう個室を予約するのですが、
今年はまさかの襖仕様。周囲の皆さま、その節は大変申し訳ございませんでした。
経営者として自分の最も重要なタスクは
「今いるメンバーで最高の結果を出す事」
それを今年もクリアし、13年連続達成したので
それは社員を労わないと罰が当たるってもんです。
「最高のメンバーだから最高の結果が出せる」
のではなく
「最高の結果が出せるから最高のメンバーだと言える」
のです。
そこは誤解のないように。
最高のメンバーにするも
最低のメンバーにするのも
経営者次第だってことです。
まあ、そんな
堅苦しい話はいったんさておき。
私個人としては一つ誓いを守ることができました。
それは「社員全員参加の一次会ではお酒を飲まない」というもの。
(えらい)
去年はベロベロになり、勢いでハシゴまでしたことを思うと、
今年は二次会にも行かずに帰宅。翌朝はスッキリ起床。
これもまた一つの成長です。
「カントリーマアムが年々小さくなっている」と言われますが、
あれはきっと私が大きくなっているだけなのでしょう。
さて。
「シラフの宴会って、楽しいんかいな?」
そう思われる方も多いと思いますが、
結論から言うと全然楽しい。
初対面や久しぶりの集まりなら、お酒の力で距離が縮まるのも分かります。
ただ、会社のメンバーとは日頃から会話を重ねていますから
無理にアルコールの力を借りなくても、十分に楽しい時間は過ごせるものです。
今回は田舎のうさんくさいソムリエ風を装い、
ワインを持って社員に注いで回っていました。
これも酔っていたら到底できない芸当です。
一方で、酔うとどうなるか。
声が大きくなる。
笑いのツボが浅くなる。
何を言っているのか分からなくなる。
グラスを割る。
水をこぼす。
記憶を失う。などなど
思い当たる方も多いのではないでしょうか。
そして翌日、決まってこう思うのです。
「ああ、昨日迷惑かけてなかったかな」と。
周囲の人はこう言ってくれます。
「楽しかったよ」
「まあ、そういう時もあるよ」
「人間だもの」
何を隠そう、私自身も散々そう慰められてきた一人。
酔っ払っている社員を見ながら、ふと思いました。
「まじで、うるせーなー」
ではなく。
「心を許してくれているんだな」
と。
冷静にお酒に呑まれず場を楽しむのも良し。
酔った勢いで弾けるのも良し。
それぞれがそれぞれの形で楽しんでくれたなら、それで万事OK。
ここで大事なのは、「人間だもの」と思えるかどうか。
つまり、
「許せるから仲間」
ということなのだと思います。
逆に言えば、許せないというのは、
まだ仲間になりきれていない状態。
そして、他人の許せない部分というのは、
多くの場合、自分自身が過去に許せていない部分でもあったりします。
これがまた、なかなかに深い。
ここで事実として言えることがあります。
周囲の人は、私たちを許してくれている。
だからこそ、今の自分があるわけです。
でも、
周囲は許しているのに、自分だけが自分を許せない人がいます。
そのプライドは、正直ダサいし、周囲にも迷惑です。
「自分を許すのも、技術のうち」です。まったく。
ダサい自分を許さないというのは、
臭いものに蓋をするようなもので
ずっとダサいままです。
それにどんなに強がったって
誰からも許され続ける自分を演じられる人なんて、
この世に一人もいませんから。
人を許せる人は、優しい。
そして、その優しさの裏には、本当の強さがあります。
そんな人になりたいものです。
さて、本題
「人間だもので良いこと、悪いこと」について。
世の中には「成功の方程式」や、それを教える本、セミナー、情報が溢れています。
不動産業界で言えば『金持ち父さん、貧乏父さん』は有名ですが、
読んだ人全員が成功しているわけではありません。
ちなみに私の継父の愛読書は『マーフィーの成功の法則』でしたが、
むしろ貧乏でした。
そもそも「成功」とは何か。
私の中での定義は、
「自分が大好きだと思える仲間の中で、
挑戦し続けられること」
一方で、多くの人が考える成功は
「経済的自由」
つまりお金持ちになることのように見えます。
私は清貧を気取るつもりはありません。
ただ、お金持ちを目指すこと自体が悪いのではなく、
お金持ちを目指し続けることが問題なのだと思っています。
なぜなら、お金は目的ではなく、手段だからです。
例えば、
3000キロカロリーの食事をする人と、
1500キロカロリーの食事をする人。
どちらが偉いでしょうか?
答えは、どちらも偉くありません。
目的が「健康」なのか、「好きなものを好きなだけ食べたい」なのか。
それは人それぞれでいいからです。
なのに世の中では、カロリーをお金に置き換えて、
比較し、競争している場面をよく見かけます。
正直、私はまったく気になりません。
そして経済面でサラリーマンが気にするものと言えば、年収。
社員にはこんな話をたまにします。
「今より100万円高い条件を出してくれる会社が2、3社ある。
それでも今の会社が好き、仲間が好き。
だから転職せず、社長に胸を張って『100万円上げてくれ』と言える結果を出す。
こんな働き方が理想やと思う」
社長が言う話として正しいかはさておき、
私は心からそう思っています。
そのためにも、 業界平均より少し高い給与水準。
完全週休二日制を含めた福利厚生。
これらを整えることは一丁目一番地。
その上で、理念や文化に合うマインドを持った人を採用するのです。
「この会社が好きで、他では働けない」(需要が無い)
「この会社が好きだが、他で働けば条件は下がる」(能力が足りない)
これはややぶらさがりで危険水準。
「この会社が嫌いだが、辞めない」
これは完全に会社にぶら下がっている状態。
会社を変えるのは経営者で、
会社を良くするのは社員。
ぶら下がっている人間が増えて、
会社が良くなるわけがありません。
だから私は、
「なんかこの会社いいよね」 「最近、勢いあるよね」
そう言われるたびに嬉しくなる反面、考えてしまいます。
自分は成長しているか。
社員は成長しているか。
チームとして、一年前より良くなっているか。
色々考えすぎて、正直夜しか眠れません。
(要するに、ちゃんと寝ています)
もとい、正直、大して変わっていないように見えるメンバーがいると、
胸が苦しくなります。
もちろん、在籍する限り見捨てることはありません。
ただし、やるか、やらないかは、どこまでいっても本人次第。
社長であっても、強制的に打席に立たせることはできません。
できるのは、本人が打席に立つきっかけを投げ続けることだけ。
うまくいくこともあれば、いかないこともある。
本人は平然としていても、私は悔しいこともあるし
正直眠れなくなる時もありました。
それくらい、社員本人より社員のことを考えているという自負があります。
まあ結局のところ、
「経営者と社員がそれぞれやるべきことをやり、
責任を果たし、成果を分かち合う。 」
そこまで「意地でも持っていく」ことが
大事なんですよ。
「結果にこだわる」って言うと嫌がる人は多いですけど
成功の果実がないから、どっちが正しい、悪いという
不毛な争いが生まれるのです。
だからこそ、問いかけたい。
「今年の自分は、やるべきことをやり切ったか?」
そして最後に、
冒頭の「許す・許せない」の話に戻ります。
もちろん、許せないこともあります。
自他ともに、許せないことベスト3は下記の通り。
① 同じミスを繰り返すこと
② 怠慢によるミス
③ 嘘をついてミスを誤魔化そうとすること
油断、妥協、諦め、慢心、驕り。
これらに基づく行為は、「人間だもの」で済ませてはいけません。
二度目はない覚悟でやってもらわないと困るのです。
なあ、自分?
そこは「人間だもの」ちゃうからな。
ドリカムばりに、何度でも何度でも言いますが、
ほんまに、そうやねんからな。
許せって言ったり、許すなって言ったり、
どっちやねんって思うかもしれませんけど、
許していい事と許したらあかん事があるってことです。
まあ、ひっくるめて
ほんまに面白い、人生は。
今日はこのへんで。
ではでは。